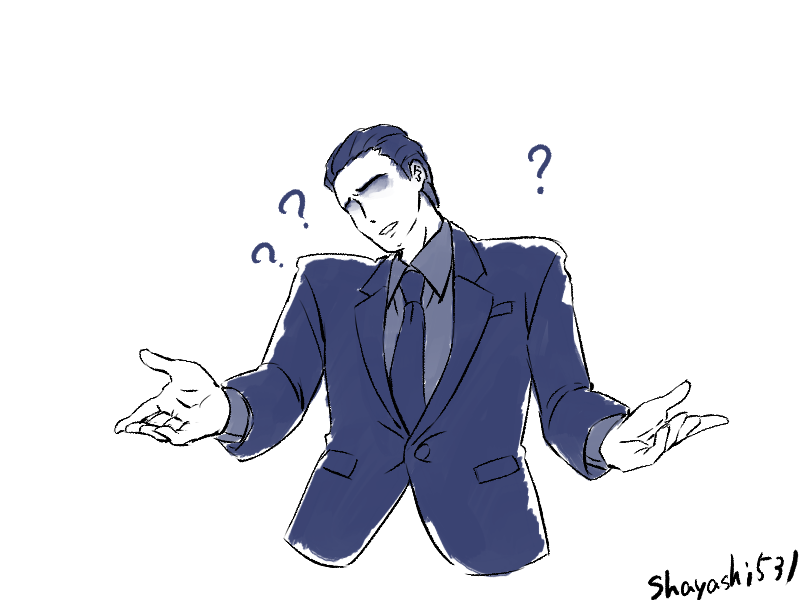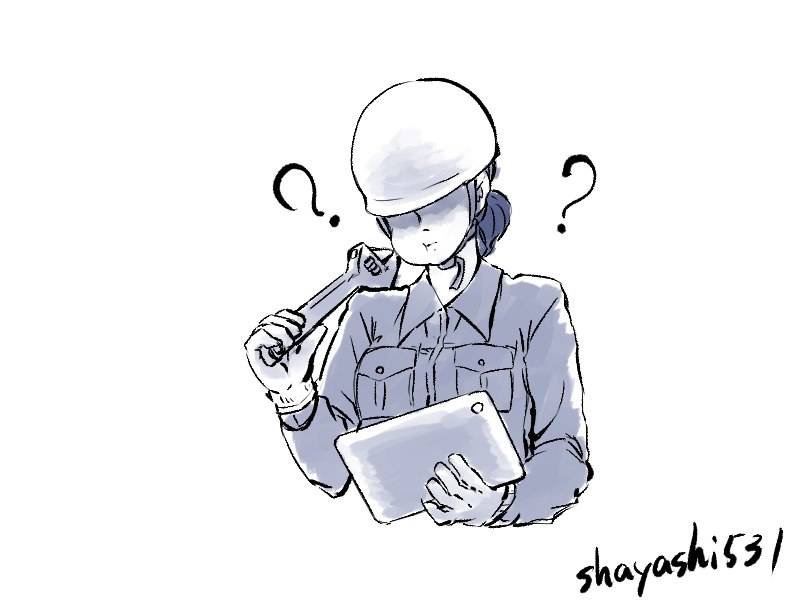
EMC関係の評価及び対策を担当されている方々は、対象機器でEMC上の不具合に出くわした際に、“こういった不具合に対しては先ずはこの対策を”と直ぐに対策方針を即座に立て、不具合処理に着手するでしょう。その方法は少なくとも50%以上の確率で上手く行き、大きな問題に発展させることなく、担当の業務を処理していると思います。これは担当者が過去に対応した対策事例を基に培われた所謂、“勘と経験”が新たなEMC課題に対して功を奏している状況であり、長い期間経験することによりその“勘と経験”は武器となり、いつしか熟練技術者としてリスペクトされる対象になっていることでしょう。
日々新商品を投入している各機器メーカー様ではEMC性能評価として熟練技術者だけではなく、新たに職場に配属された若手や他分野の技術者(EMC分野の新人)もEMC対策の現場に臨まされていることでしょう。EMC対策の経験の少ない新人の方々にとって、EMC課題に出くわした時に不安になることは課題対策として先ず“何をすべきか”、ではないでしょうか?この“何をすべきか”、を思った時に先ずは“基礎や原理から学ばないと”、と思われた方は、真面目な方だと思います。本当にその通りです。ですが、その道のりはご自身の過去の専門分野にもよりますがとても時間が掛かります。高周波回路学や電磁気学はそう簡単に理解できるものではありません。また、市販されているEMC関連のハウツー本が手っ取り早そうに見えたりしますが、実は学術的にあまり適切ではない解説がされているものもあります。
例えば、電磁気学的な理解ができていないMaxwellの方程式の説明とか、電磁波(ノイズ)伝搬の考え方、電流における電荷と電子の概念の違い等、他にも沢山あります。更に残念なのは現在多用されているロジック半導体のCMOSトランジスタに関する知識が乏しいことで、古めの書籍(かつての技術屋さんの記事?)ではバイポーラトランジスタで説明しているものがあったりします。世の中、次から次へと新刊のEMC関連書籍が出てきていますので、選択方法の一つとしてバイポーラトランジスタを使った回路図の記載があったら、その書籍はやめた方がよいでしょう。“回路の動作原理は同じでは”、と言われる方がいるかも知れませんが、電流・電圧の使われ方が異なりますのでEMC対策のやり方も変わります。
それでも、EMC関連のハウツー本等で知識(適正かどうかに関わらず)を得たとしても多分その知識によってEMC課題を解決する上ではあまり役に立たないでしょう。何故ならば、それぞれのEMC課題に対して実際にやるべきことが書かれていないからです。基本的にはハウツー本等での知識を基に実際の活動は“自分で考える”、ということを期待されているからです。
“自分で考える”はどんな仕事でも期待されることですが、EMC関連のハウツー本からでは難しいだろうな、というのが当方の思いです。
当社はPD適用(基礎編・実践編)とSD適用(基礎編・実践編・差動編)をEMC関係の方々に、EMC対策・EMC設計で先ずやるべきこととして紹介しております。ユーザーの方々はSimツールを使ってそれらのノイズ低減効果を体験して頂けます。またそれを通してノイズ低減における最低限の知識や気づき・納得感を得てもらうためのセミナーとして“EMC設計 MBDでDX! 技術&学術”を用意しております。更にWDでは回路基板のアートワーク設計で、検討したEMC設計を回路基板上に実践するためのデザインルールを紹介しております。
熟練技術者でも解決に結果として時間を要してしまったEMC対策の経験も30%程度はあったのではないかと思います。その際に感じることとして、やっぱり“EMC課題解決には原理・原則だ”、ということを思うのではないでしょうか?その30%に貢献できるのも当社のセミナーではないかと思っています。
※関連ページ
5. 回路基板におけるEMC設計の実践と検図。当社のWDを提案。