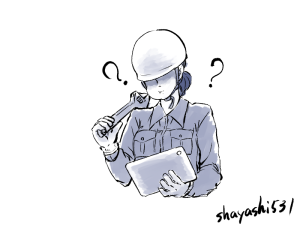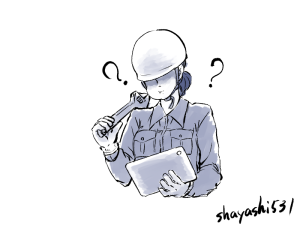
電子機器等のセットメーカーの技術者の皆様が、EMC関連業界の方々のセミナー及び記事からEMCに関する情報を入手する機会が増えていると思います。そういった情報の中で電子回路設計に携わってきた方でEMC関係者が使う専門用語に違和感を覚えたことは無いでしょうか?
私にとって最も違和感があったのは“コモンモード”でした。この用語と対になるのが“ディファレンシャルモード”で、この2つの用語はN個の電源とN個の終端が共通のGND極と対をなす異なるN本の活線路(ライン)がある時に適用されるものです。実際の電子機器の回路ではN=2の形態、即ち差動伝送路に適用され、一方のラインa、他方のラインbとするときの電圧に関して、
ディファレンシャル(差動)モード電圧 ・・・ Vdiff = Va – Vb
コモン(共通)モード電圧(1/2を掛けて平均値とする場合も)・・・ Vcom = Va + Vb
と定義され、ディファレンシャルモードとコモンモードは互いに直交ベクトルとしての意味合いも持ちます。上記のVをIに変えればその電流となります。この差動線路の基本的な構成は2本の活線ラインとGNDライン(電極)の3本の電極パターンにより構成されます。
しかし、EMC関係者の扱いではN=1の時(一般的にはシングルエンドの形態)に当たる場合でも、信号・電源ラインとその対となるGNDの2本の電極に、当該機器のフレームのGNDとか外部の仮想的なGNDを3個目の電極と想定してか、ディファレンシャルモード・コモンモードの呼称を当てています。
“そういうものか”と納得される方もいるかも知れませんが、私などは下記の様な疑問を持ってしまいます。
①電源・信号ラインがなぜ差動といえるのか?電源又は信号源の電圧を伝送する線路は差動ではないでしょう。実際の差動線路に当てはめたら各線路が差動で更にその線路間にも差動が存在するというややこしい関係になります。
②GND電極同士は電気的にDC接続の箇所を持った同極なので、基本的に同電位を持つでしょう。
③ディファレンシャルモードがコモンモードに変換されるという説明をされる方がいますが、差動線路であればSパラメータなどの数式で定義することが可能です。しかし、基本的に2本の線路にSパラメータのようなモードの変換を定義づけできるようなものはありません。
しかし、“単相100V等の電源回路ではコモンモードチョーク(フィルタ)が部品として存在する”とご意見される方も居られると思います。
これに関しては少し説明致します。このコモンモードチョークは電源回路の1次側に設定されます。電源1次側には通常、L(ライブ)、N(ニュートラル)、E(アース)の各端子があり、その電位の関係でNとEは略同電位で、機器外の分電盤でNはEに接続する関係になっています。また、電源回路の2次側の回路構成の関係で作られるGND電位の電極はその直流電位を電源の1次側のEに接続して電位を0Vにする操作を行っています。但し、このGND電極が機器内で直接N端子に接続することはおこなわれていません。
ただこのGND電極は機器内の回路の電源・信号の対となるGNDになっているため機器内の回路の高周波成分(ノイズ)が、その回路を介して電源回路のL及びNのライン側までEの電極(GND)と対になって漏洩していくリスクが生じます。そのため、L、Nのラインノイズをチョークするためにコイル(フィルタ)が挿入されます。ここで、L、Nのラインのそれぞれにチョークコイルを入れればよいとも考えられますが、L、Nのラインには機器を動作させるための(比較的大きい)商用交流電流が流れるので、それぞれのチョークコイルの磁器コアの磁気特性が飽和してチョークの効果が低減してしまいます。
これに対し、L、Nのラインには反平行の状態で商用電流が流れる性質を活かし、チョークコイルの磁器コアにL、Nのラインを所謂コモンモード巻きで行うことにより、磁気コアの磁気特性の飽和を起こさず、L、Nの各ラインの高周波成分(ノイズ)の漏洩に対してチョークさせることができます。
このような構成からコモンモード巻きのコイル部品をコモンモードチョークと呼んでいるのであって、本質的には差動線路におけるコモンモードのノイズ対策とは異なるものです。
当ホームページでは、2本の電極対はそれぞれの電極で電流は反平行(⇄)の状態で伝送していくことを“25. これがグラウンド(GND)を流れるリターン電流!”のページで解説してきました。そのことからすると、そもそもラインを流れる電流に対してディファレンシャルモードと呼ぶのは適切ではないのです。
ただまあ、そうは言うものの実際のEMCの現場では電気回路学からのイメージで、“ディファレンシャルモード”、“コモンモード”の呼称が特に意味なく惰性的に使い続けられていくと思います。しかし、時にはその背景を理解して頂き、EMC設計を考えて頂きたいと思っています。
※関連ページ
-
-
-
EMC設計、GNDの機能を解説
EMC設計 MBDでDX! 技術&学術