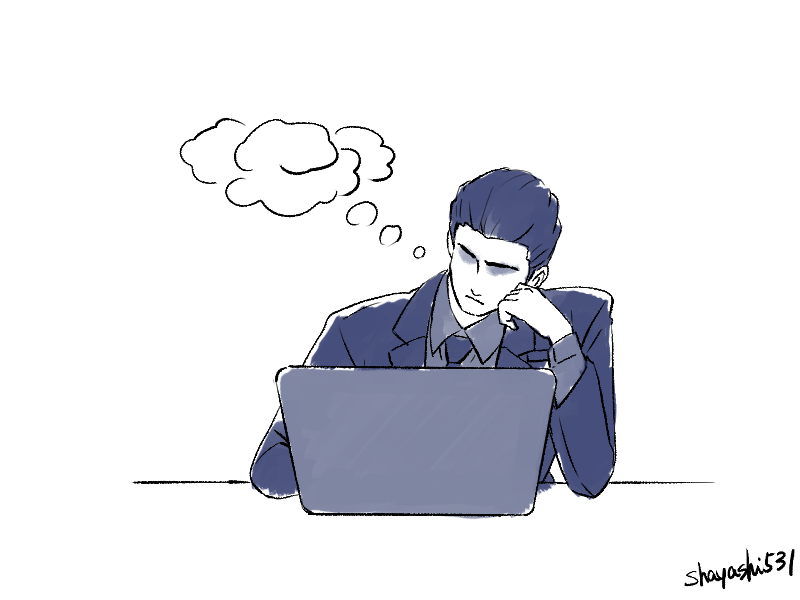
機器設計で初期の想定よりも実機の試作段階で実稼働時の発熱が課題となる場合、熱対策として発熱するICにヒートシンクを新たに取り付けたり、既にヒートシンクが付いている場合はヒートシンクとICの間に熱伝導をよくする材料(グリスやシート)を挿入したりします。
この時、”熱対策後に不要輻射(EMI)が悪化した”、という経験を持つ現場のEMC技術者が多くいると思います。場合によっては、ノイズの測定値がEMIの規格値を超えてしまって、その対策が上手く行かずかなりてこずった経験をお持ちの方もいるでしょう。こんな時、EMC技術者の方々は新た生じたEMI課題のメカニズムにどんな想定をするのでしょうか?
私の経験した設計の場では、”付加したヒートシンクが新たなアンテナとなってノイズを放射した”、とか、”ICの表面とヒートシンクが容量結合して新たなノイズの伝達するパスが形成された”、等というメカニズム(モデル)を考える方々が多くいました。しかし、そのモデルで実際に電磁界解析してみると、期待したようなノイズ放射の増大を観察することはできませんでした。そもそも、”ICの表面とヒートシンクの容量結合”がどの程度想定できるでしょうか?仮にその容量を1pFとすると、そのインピーダンスは約1.6kΩ(@100MHz)となるので、ノイズの容量結合を考える上では容量値を大きめに想定する必要があります。しかしIC内のチップの面積(ダイサイズ)はそれほど大きなものではなく、チップとヒートシンクに介在する誘電体も比誘電率が一桁台の材料なので、10pFを超えるような容量値の設定には無理があると考えられます。
そこで熱対策の前後で何が変わったのかを改めて考えてみます。上記の想定モデル(メカニズム)は誰もが外観(見かけ)の変化から発想するものです。しかし、変化はそれだけでしょうか?よーく考えると、熱対策でICの放熱が改善される、即ちそれはIC内のチップの温度が低下していることになるのです。
将に、このICチップの熱低下(冷却)が重要であって、半導体の特性として低温になるとトランジスタのスイッチング速度が向上し、即ちそれは生成されるパルス形波のスルーレートを向上させます。そしてそれはパルス波形の高周波成分(ノイズ成分)が増大することを意味するので、その帯域が十分に対策されていなければ熱対策後にEMIの悪化となって現れます。
簡単に言えば、”熱対策をするとノイズ源のパワーは増大する”、と言うことです。
そのため、熱対策を必要とする機器の設計では事前に十分なEMC設計が必要となります。現場での熱対策を取りながらEMI対策を行うのはとても厄介な作業で、現場のEMC技術者を窮地に追いやる状況になったりします。 熱対策を必要とする機器を設計する際には事前のEMC設計が非常に重要です。当社の”SD適用”、”PD適用”を回路図設計段階で是非ご検討頂きたいです。